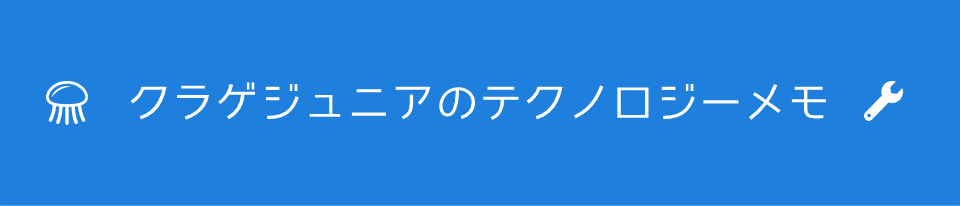2022年06月02日 更新
HDD消去ツールwipe-outの使い方
どうも、クラゲジュニアです。
最近、Windows PCに対して、無料ハードディスク消去ツールwipe-outを使ってハードディスクを消去しました。その備忘録を兼ねて使い方とポイントを紹介します。
USBメモリを使ってwipe-outを起動する例で説明します。
[TOC]
ツールのダウンロード
こちらのページからツールをダウンロードすることができますが、いくつかのバージョンがあります。

最新のバージョンだとテスト中で、古いバージョンだとバグがあるようなので、ほぼ正式版と書かれているものを選びました。
今回はUSBメモリなのでUSBイメージ版をダウンロードします。
USBメモリへイメージ書き出し
ダウンロードしたファイルを普通にUSBメモリへコピーしてもNGです。
「イメージ書き込み」という方法で行う必要があります。
イメージ書き込み用の様々なフリーソフトがありますが、今回はWin32 Disk Imagerを使いました。

使い方は簡単で、ダウンロードしたファイルを読み込みます。ファイル選択時は拡張子.usbが選べるようにしてください。書き込み先のデバイスとしてUSBメモリのドライブを選んでwriteをクリックすることで出来ます。データが消えますので、間違ってもUSBメモリ以外は選ばないように注意してください。
USBメモリをPCに挿して起動
USBメモリを消去したいHDDがついているPCに挿して起動または再起動します。 FreeBSDというOSが立ち上がり、しばらくして以下のような画面になれば成功です。

※この画像は古いバージョンのため、メニューの並び等は異なります
これでwipe-outが起動しました。
wipe-out が起動しない場合
PCを再起動しDelキーなどを連打してBIOS画面を起動します。
キーはマザーボードによって異なり、F2やF1の場合もあります。

※画面はマザーボードによって異なります
起動デバイスの優先順位について、USBメモリが内蔵HDDより上になるように変更します。なお、BootモードがUEFIだとダメな場合がありますので、その場合はLEGACYに変更してください。
具体的な方法は「BIOS 起動順位」などでググってください。
wipe-outの操作
マウスは効きませんのでキーボードのカーソルキーとEnterキーで操作します。
現在選択中のディスクは・・・です。の部分で対象のHDDが選択されているか確認します。異なる場合は、別のディスクを選択するというメニューを選びます。
様々な書き込み方法がありますが、複数回上書きして、このディスクのデータを念入りに消すを選びました。

※この画像は古いバージョンのため、メニューの並び等は異なります
実行時間はHDDの容量などPCのスペックによって異なります。ちなみにクラゲジュニアの環境ではHDD 500GBに対して3時間弱かかりました。
終了すると、ビープ音で「キーンコーンカーンコーン」というメロディーが鳴ります。スヌーズ機能があるようで、放置していると10分置きくらいに鳴り続けます。これで完了です。
USBメモリを使えるように戻す
イメージを書き込んだUSBメモリをフォーマットすると、16GBあるはずの容量が数MBになっていました。
以下はこれを元に戻す作業です。
Windowsの検索メニューからディスク管理と入力し、以下の内容を開いてUSBメモリのディスク番号を確認します。

Windows + Rキーでファイル名を指定して実行ボックスを開き、diskpart と打ち込みます。

コマンドプロンプトが起動されるので、以下を打ち込みます。番号は先ほど確認したディスク番号です。
list disk
select disk 2
clean
create partition primary途中1回失敗しましたが、cleanをもう1回打ったら大丈夫でした。
エクスプローラーからUSBメモリをダブルクリックしてみると以下が表示されます。

これでフォーマットを行うことにより、容量が元に戻りました。
以上です。